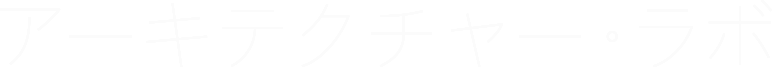- コラム
慌てずにお焚き上げの準備を
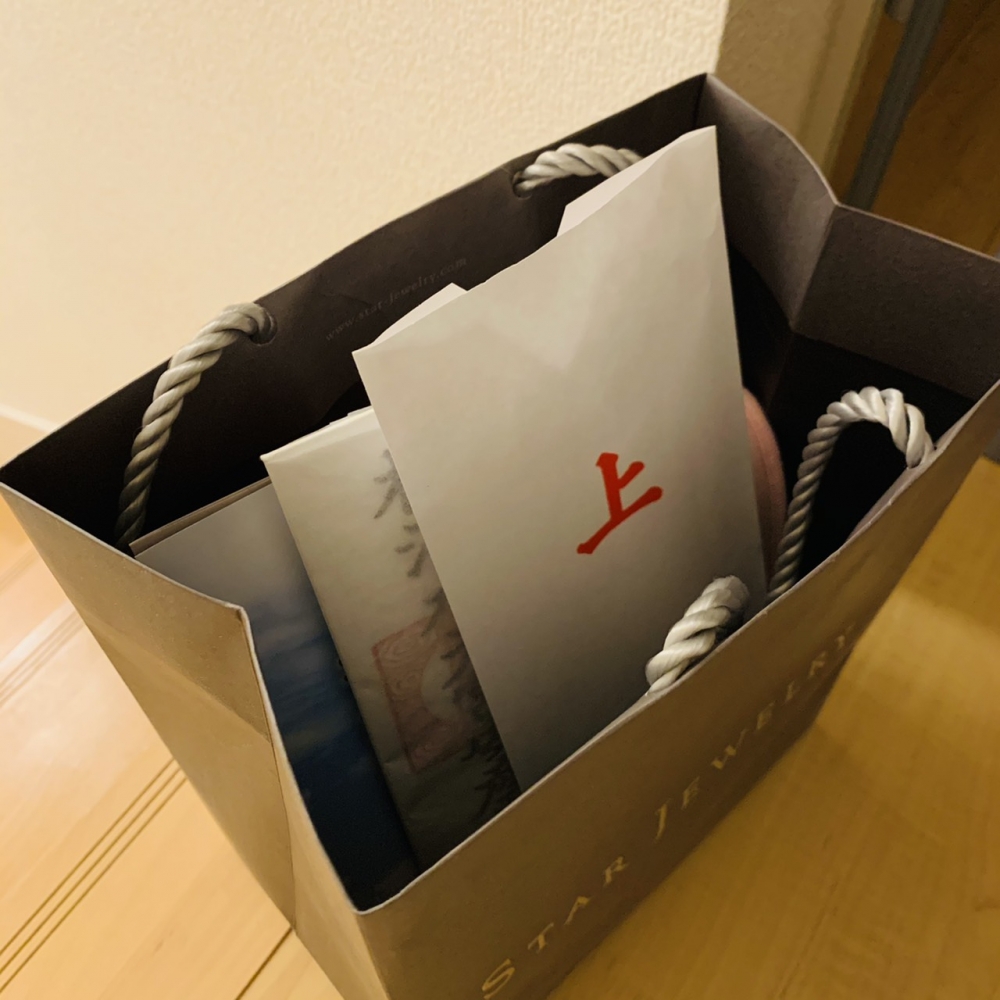
皆さん、大掃除は順調に進んでいますか?
家のあちこちを見て回るのと並行して、
1年間護ってくださった御札や御守りを納める用意もしていきましょう。
多くの神社では年末や小正月(1月15日)に、お焚き上げをしてくれます。
年末年始の帰省や、
初詣の際に持ち出しやすいように1つ紙袋を用意しておくと良いです。
紙袋ならそのまま燃すこともできますし、
静かな境内でガサガサと音を鳴らすことも避けられます。
お焚き上げは、地域によって左義長・どんと焼きと名前が変わるのもおもしろいところ。
ご存知の方も多いことと思いますが、
改めてお焚き上げについておさらいしておきましょう。
お焚き上げを詳しく知ろう
お焚き上げの由来は、庭燎(にわび)といわれています。
庭燎とは、庭でたくかがり火のことで
神事でたいていた火が語源であるとされています。
日本では昔から、大切にしたものには魂が宿るといわれますよね。
その魂を浄火して天上へ戻すための儀式?が、お焚き上げです。
お焚き上げをしてくれる場所は、大きく分けて2つ。
1つは、神社やお寺などの宗教施設。
そしてもう1つは、遺品整理やお焚き上げを専門に行う業者です。
それぞれのメリット・デメリット
神社やお寺でお願いする場合、
メリット →金額が安く済む(お気持ちで)
デメリット→品物によっては受付不可、受付時期が限られがち
専門業者にお願いする場合、
メリット →基本的に何でも受付てくれる、割と年中対応してくれる
デメリット→神社やお寺に比べて高額
専門業者にお願いすると、火葬の際に一緒に入れられなかった物などを
引き受けてくれることもあるようですよ。
その他 お焚き上げ情報
お焚き上げをしてほしい神社やお寺が遠方の場合、
問い合わせをすると郵送にて受付てくれる場合があります。
また、大きな品物の場合にはお焚き上げで断られても
神棚処分という形で祈祷料金を支払うことで受付てもらえる場合も。
(この辺りは、各神社・お寺によって異なりますので詳しくは要確認を)
ちなみに我が家は、神社でもらったフリーペーパーや御守りを
授けてもらった時の袋・御神籤などもお焚き上げに持っていきます。
なんだか普段のゴミと一緒に捨てるのは、
気が引けてこうしているのですが、皆さんどうしていますか?
(リンク先が新しくなりました!フォローをお願いします)