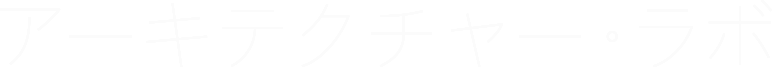- コラム
今はなき大仏殿に想いを馳せる

“鎌倉の大仏”で有名な、鎌倉大仏殿高徳院へ行ってきました。
(露坐の大仏 国宝銅像阿弥陀如来像)
鎌倉で唯一、国宝指定となっている仏像でもあります。
大仏は1252年に造られ始め、
現在でもほとんど造立当初の形を残しているといわれています。
しかし、何の目的があって誰が造ったのかは
未だハッキリしていないという、謎多き大仏です。
ちなみに、大仏の眉間にある白毫(びゃくごう)って何だかご存知ですか?
白毫は右巻きの白い毛の塊とされていて、
ここから人々を照らす光が発せられると言われている場所。
白毫をはじめとし、仏と常人には32の身体的違いがあるとされています。
失われた大仏殿
はじめに“露坐”と書きましたが、
露坐とは屋根のないところに居座ることを意味する言葉。
実は、現在でこそ鎌倉大仏は露坐であるものの、
室町時代までは国内最大の大きさを誇る奈良の大仏と同じく、
屋根と壁を有する大仏殿のなかに鎮座していました。
何度も災害に見舞われ、その度に倒壊・修復を繰り返した大仏殿ですが、
ついに明王の大地震により崩壊し、
その後新たに建てられることなく今日に至ったとされています。 ※諸説あり
実は…少しだけ残っています!
建築好きとして気になるのは、消失してしまった大仏殿。
(大仏には申し訳ないですが…!)
実は今はなき大仏殿、少しだけアイキャッチ画像に写っているのわかりますか?
右下 手前に写る大きな石、これ大仏殿の礎石なんです。
礎石とは、建築の基礎にある柱などを支えてくれる石のこと。
大仏殿の高さは40メートルを越える巨大建築だったそうで、
礎石も1つ1つがとても大きいです。
礎石をよく見ると、の芯出しのためにつけられたであろう
十字の跡や鑿で削り出した跡も見ることができます。
礎石とは知らずか、今はベンチ代わりに使われているようですが…。
大仏に負けず劣らずこちらも大変貴重で、
実は鎌倉大仏殿跡として、国の指定史跡でもあります。
次に鎌倉大仏殿高徳院へ訪れる際には、皆さんもぜひ礎石にも着目してみてくださいね。