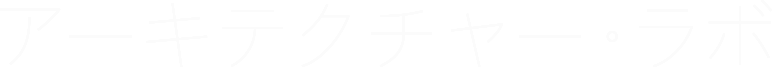- コラム
年賀状に関する豆知識

さて、2020年もついに終わりです。
1月1日に届くようにするためには、
12月25日までに投函しなくてはならなかった年賀状ですが
「今も書いている最中だよ…」という方も、実はいらっしゃるのでは?
今日は、年賀状に関する豆知識についてお話しますね。
まずは、皆さんご存知のあたりから。
年賀状には、年賀ハガキ以外の一般的なハガキも利用可能です。
その場合には、朱色で表に“年賀”と記載することを忘れずに。
年賀状の歴史について
実は年賀状というのは、とても古くからある文化の1つでして
文献をさかのぼっていくと
平安時代にも年賀状文化があったことが確認できるそうです。
お世話になった方や親族の家をまわる文化である年始回り。
(いまでも営業職などでは多少残っていますね)
この年始まわりを簡略化させたものが年賀状であり、
年始回りの衰退が、年賀状を普及させたともいわれています。
投函口を誤るとどうなる?
さて、話を現代に戻します。
年賀状の収集がはじまると、
ポストの投函口が一般郵便と年賀郵便に分けられますよね。
誤って年賀状を一般郵便の投函口へ入れてしまった場合どうなるかはご存知ですか?
正解は…、
仕分けの際に年賀状として扱ってもらえるので、基本的には問題ないそうです。
ただし絶対ではないので、やはり各々が正しい投函口に入れることが大切。
郵便局員さんの無駄な手間を増やさぬよう、気をつけましょうね。
ちなみに、相手方に届く前でしたら、
投函した郵便物の差し戻し請求なんてこともできるそうです。
デジタル派?アナログ派?
 郵便局のHPによると、
郵便局のHPによると、
2021年用の年賀ハガキ当初発行枚数は19億4198万枚とのこと。
何でも電子化されていく世の中ですが、
私はこの枚数を見て
「意外にも年賀状は紙で出すアナログな人が多いのね」と思いました。
皆さんはどう思われますか?
アナログついでにご紹介、私のお気に入りの
STAEDTLERのコンクリートボールペンです。
設計製図をする方には、STAEDTLERは馴染みのメーカーですかね。
筆記用具に適した独自開発のコンクリートが用いられている、というおもしろい製品。
見た目のわりに?、とても軽くて書き心地も良くておすすめです。
それでは今年も残すところあと数時間。
今年も大変お世話になりました、良いお年をお迎えくださいませ。
(リンク先が新しくなりました!フォローをお願いします)