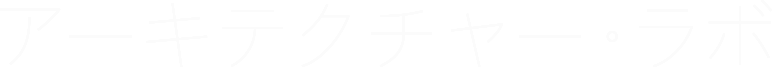- コラム
建築ストック大国 日本

これからの建築業界では、
いままで貯めに貯めた(溜めた)ストック建築の経営・文化財建築の経営が
一つの大きな仕事となると思われます。
世界的に見ても、“日本はストック建築大国”といって恥ずかしくないくらいのストック量です。
住宅に限った話だけでも、ストック量の多さは明らかです。
2018年時点で、住宅ストック数は約6200万戸、総世帯は約5400万世帯。
世帯数に比べて、約16%上回る住宅ストックがあるのです。(参考 )
これらは、国民総出の投資による賜物であり、
ストック自体は恥ずべきことではありません。
がしかし、先にも述べたように経営していかなくては、
維持管理さえもままならない状態となりうる危険性があるのです。
例えば、UR都市機構赤羽台団地の既存住棟(41、42、43、44号棟)の
保存活用に関する要望書が出されたことも記憶に新しいのではないでしょうか。
(板状階段室型41号棟・ポイント型ハウス(スターハウス)42〜44号棟)
団地が、国の有形登録文化財にと申請されたこと自体初めてでしたが、
強い公共性が認められ日本建築学会内に専門委員会も設けられ、
今後どういった保存活用をしていくか2019年〜話し合われています。
「期限つきで実際に団地で暮らし、あなたが活動の中心的存在となってみませんか?」
という旨のプロジェクトも多数あります。
団地暮らしやコミュニティ作りに興味のある方、手を挙げてはいかがでしょう?
地域にどのような形で貢献するのか、
また団地でどのような収益を上げていけるのか、腕の見せどころです。
団地再生としてよくあるのは、“地域交流の場”との名前で
高齢者が日中集まって会話をする場として活用されること。
一室くらいは使用用途として埋まるかもしれませんが、
ここで利益を発生させたり、ここからさらなる拡がりを産みにくかったりするのが難点。
井戸端会議に無料で場所を提供し続けているようなことですからね…。
せめてこの場を管理する人がいて、
さまざまなイベントを企画していかなくては利益には繋がりません。
建築は、設計が全てではありません。
利用する人が居てこその建築ですから、皆さんも一緒に問題に取り組みませんか。
建築の未来を、一緒につくっていきませんか。