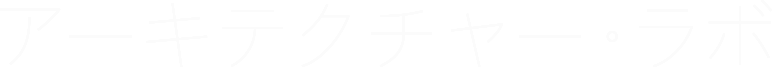- コラム
框

今回は、框(かまち)についてお話しします。
ほぼ全ての住宅にあるのですが、
框はどこにあるどのような部分を指している言葉かご存知ですか?
建築用語のなかでも、馴染みが薄い言葉かもしれません。解説していきます。
豆知識
元々框とは、「周りを囲む枠」を意味していました。
そのため、窓や戸・障子などの枠や、
畳の縁がついていない端の部材も全て框と呼んでいました。
今では縁を補強する木材を指すことが一般的です。
框の種類
 1.上がり框
1.上がり框
玄関の、靴を脱ぐ部分とその先の廊下(または部屋)につながる部分には段差がありますよね。
この段差の端に取り付けられている横木が、框です。
玄関扉を開けた時に、視界に入って来る部分なので見た目の良さが重要視されます。
また出入りをする際に、必ず通る部分のため耐久性も求められます。
一般的な戸建ての場合、上がり框の高さは15〜18cm。
賃貸アパートやマンションですと、5〜7cmと少し低くなっています。
上がり框が高いと…
・座って靴を履いた時に立ち上がりやすい
・高齢者や子どもは段差の上り下りが億劫
上がり框が低いと…
・スッと上がることができて楽
・子どもが小さいうちは靴の脱ぎ履きをしやすい
・座って靴を履いたり重たい荷物を背負ったりしていると立ち上がりにくい
それぞれに良い点・悪い点がありますが、
子どもは成長していくので高さは大人に合わせ、
壁には汚れ防止も含めて手摺を設置するのも1つの手段です。
2.床框(または床縁)
これは和室にある、床の間についている框の呼び方です。
床の間は、掛け軸や生花・骨董品などを飾るための場所です。
“永久(とこしえ)“と掛けられているという説もあり、
家の繁栄を象徴する神聖な場所とされています。
そのため他の床より一段高いので、床板や床畳を隠すために框が取り付けられているのです。
最近の住宅では、畳の部屋はあっても床の間はなかなかないですね…。
古民家や茶室を訪れた際に、ぜひ確認してみてください。
 3.縁框
3.縁框
縁側の外側の端部に取り付けられている框を、縁框と呼びます。
雨戸を取り付けるために、上部に溝が設けられることがあります。
いかがでしたか?
聞きなれない言葉である框が、じつは生活のすぐそばにあるものであると
少しでも伝わると幸いです。