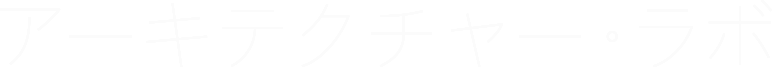- コラム
2022年問題 生産緑地とは

1992年に生産緑地法のなかで定められた土地制度の1つに、
「
最低でも30年間は、農地や緑
優遇内容
生産緑地になるためには、
500㎡(2017年に改正され300
30年は解除不可・農林漁業を継続と
日本全国どこでも設定さ
生産緑地は、三大都市圏(首都圏・中部圏・
1992年から30年の節目となる、2022年。
生産緑地の約8割が、期限満了を迎えると言われており、
「税制優
「代替わりした
土地を手放
手放された都市部の農地は宅地へと転用され、新築住宅が多く建て
住宅の過剰供給・空室の増加・不動産の価格暴落が起こるの
いわゆる「2022年問題」
宅地転用までの道のりは楽じゃない
指定解除された土地が全て宅地へと転用できるのではありません。
市区町村は時価で買取りを行いますが、
予算の都合もあ
次に、市区町村が買取らない場合には、農林業に従事することを希
土地を買いたい人が3ヶ月以内に現れなかった場
ようやく自由に土地を売却できるようになり宅地へと生まれ変
 政府もこの問題の対策に乗り出しました。
政府もこの問題の対策に乗り出しました。
一気に土地が放出されるのを防ぐため、生産緑地とは別に、
「特定
特定生産緑地は、所有者の
10年間の延長措置(固定資産税の軽減や相続税の納